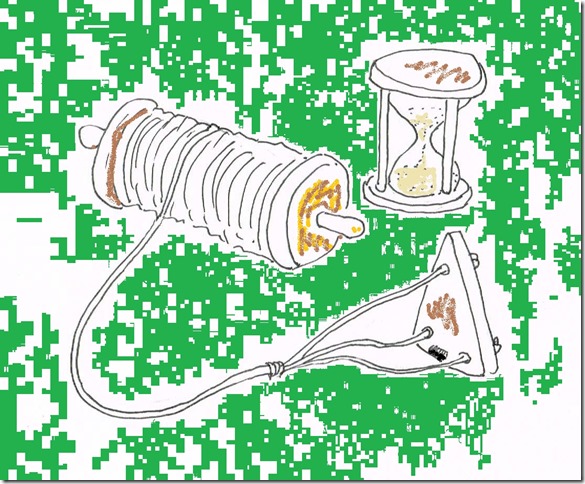米窪太刀雄(よねくぼ たちお)著
夏目漱石も激賞した商船学校の練習帆船・大成丸の世界周航記。
若々しさにあふれた商船学校生による異色の帆船航海記が現代の言葉で復活(連載の第18回)
陣風(スコール)
明治維新より前には箱根から西には化物(ばけもの)や、ももんがあが、うじゃうじゃとひしめいていると信じられていた。しかし、今は時代が進んで、陸上(おか)では、吉原に花魁(おいらん)を買いにいく女の客が出現するというご時世(じせい)で、お化けもすっかりその株を奪われて、どこかに隠れて息をひそめているが、海上ではまだまだお化けや幽霊がわかった風な顔で、さかんに船乗りをてこずらせている。
颶風(ぐふう、サイクロン)がすなわちそれである。しかし、この海上のお化けも百八十度の子午線を境界(さかい)にして、東の方にはまったく姿を見せないという奇怪な現象を示している。これはお化けの原産地でもあり、また根拠地とも信じられているのはインド洋中のモーリシャス島で、年々三十を超える化物どもを遠慮会釈もなくどしどしと日本近海に輸入してくる。ところが、同じお化けでも紅葉狩りでは鬼女となり、三十三間堂の現れては柳の精となり、道成寺の清姫では蛇の化性(けしょう)となったように、颶風(ぐふう、サイクロン)も中国近海では台風(タイフーン)と呼ばれ、インド洋では颶風(ハリケーン)と早変わりし、日本近海では旋風(サイクロン)として恐れられている*1。
で、ここでは船乗りから疫病神のようにこわがられている颶風(ぐふう)を真っ向から罵(ののし)るのは後々の祟(たた)りもあり、また中国の古い兵法に樹木を枯らすにはまず枝葉を切れとあるので、それに従って、颶風のお化けの家来(けらい)格で、また独立した斥候(せっこう)ぐらいの資格で神出鬼没に遊動する陣風(スコール)をまずはやっつけておこう。
この陣風(スコール)にも二種類あって、兄貴株は黒雲陣風(ブラックスコール)といわれ、弟分は無雲陣風(ホワイトスコール)と号している。たいがいの場合、このスコールなるものは親分のお化けの露払(つゆはら)いか、太刀持(たちも)ちとしゃれこんでビュービューとやってくるが、腹の虫の居所がちがっているときには、何らの先触(さきぶ)れもなく最後通牒(さいごつうちょう)もなく、だしぬけにガッとくるところは、どこかの国の宣戦布告に似ている。であるから、船乗りはスコールを海上の横紙破り、海上の腹黒者(はらぐろもの)と呼んでいる。風はやわらかだし、海はおだやかでサイクローンのサの字も見えないので天下泰平(てんかたいへい)国家安康(こっかあんこう)と、気を許してウカウカ進んでいったものなら最後、鈴鹿峠の山賊の手からのがれた旅人が、三島の宿(しゅく)の護摩の灰(ごまのはい)に有り金をスッカリせしめられるような目にあうのである。
この兄弟分のスコールも颶風が百八十度線以東に見えないときは、百八十度の子午線を境として、あんたはこの線の西、自分はこの線の東を領地とするとでも区分したのか、黒雲のスコールは百八十度の経線の西に多く、雲のないスコールはその東にのみ見られる。しかも、この弟分の方は兄貴分が荒々しく激しいのに反し、性格はすこぶる穏やかで、江戸っ子のような口ぶりで腹白(はらじろ)で気性もさっぱりしている。盆を引っくり返したような激しい雨がザーッと船を白く靄(もや)に包み込んだと思うと、どういうことか、いつのまにか癪(しゃく)にさわるくらい、すっかり日本晴れで晴れ渡っている。しかし、風力はなかなか強い。
せわしく響く靴音とともに、当直士官の甲高い声が聞こえる。「総員上へ! 雨浴(うよく)許す」と、なんとも珍妙な号令が下る。
船での生活で船乗りの最も熱望するものはと問われると、その返事には必ずや明るい空気の下で真水をあびることと、まだインクの香りがする朝の新聞になるだろう。で、人々は争って雨を浴びる。否、滝をあびる。かくて、連日のチリとホコリとをぬぐいさってしまうと、爽気(そうき)身にしみわたって、きらびやかで豪華な服をまとった将軍のような、至極おめでたい日本一のご機嫌となる。なかには浴びそこなって半分石鹸を体になすりつけたまま、いままでの修羅場はどこへやら、風はそよともせず波は笑い、ただ西の空に色彩鮮やかに美しくかかっている虹で、わずかにそれとわかるだけで、心にくいほどにケロリと晴れ渡った天気を、うらめしそうにながめている笑止の姿も見受ける。
というようなことを、かつて在校中に運用術の時間に亡くなられた太河平(たこひら)教諭が実体験としてよく語られていた。
(横線)
脚注
*1: 強風/暴風雨について、さまざまな表現がなされているが、現代とは表現が異なるので、整理しておこう。
現代では、風の強さ(風速)を13段階に分けたビューフォート風力階級が用いられている。
風力0(平穏、風速秒速0~0.2m)、
風力1(至軽風)、風力2(軽風)、風力3(軟風)、
風力4(和風)、風力5(疾風)、風力6(雄風)、風力7(強風)、
風力8(疾強風、秒速17.2m~20.7m、このレベルから台風)、
風力9(大強風)、風力10(全強風/暴風)、風力11(暴風/烈風)、
風力12(颶風(ぐふう、秒速32.7m以上、ハリケーンやサイクロンはこのレベルから)
ちなみに一定の風速を超えるまでに発達した熱帯低気圧は、発生した場所により
台風: 西太平洋、日付変更線≒東経180度より西
ハリケーン: 東太平洋、大西洋(カリブ海を含む)
サイクロン: インド洋、南半球の太平洋
となる。
もっとも熱帯低気圧は移動するため、途中で呼び名が変わることもある。
東太平洋で発生したハリケーンが西進して台風と呼ばれるようになったりもする(越境台風)。
スコールは急に降り出す強風を伴った雨のことで、気象用語として、黒雲を伴うブラックスコールや雲がないホワイトスコールという表現は現代でも用いられている。