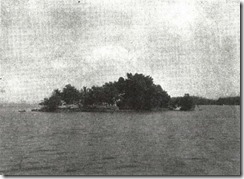第十六章
ピジン語*1
白人の交易商人の数が多いこととエリアが広いこと、原住民の言語や方言が二十以上もあるということになれば、交易商人たちは、まったく新しい、科学的とはいえないものの、完全に実用に適した言葉を作り出す。そうやって実際に作り出された言葉の例が、ブリティッシュ・コロンビアやアラスカ、北米のノースウェスト地域で使われているチヌーク語だ。アフリカのクルメン族の言葉や極東のピジン英語、南太平洋西部のピジン語もそれに該当する。このピジン語というやつ、広い意味でピジン英語と呼ばれることが多いが、いわゆるピジン英語とははっきり違っている。どれくらい違っているかについては、中国語で伝統的な数に関係してピーシーを使うことがないという事実を指摘すれば十分だろう。
たとえば船長が現地人のボスを船室に呼ぶ必要があり、そのボスが甲板にいるとする。船長は中国人の接客係には、こう指示する。「ヘイ、ボーイ、ユー、ゴウトゥ、トップサイド、キャッチー、ワン・ピーシー・キング(おい、君、上まで行って大将をつかまえてきてくれ)」 接客係がニューヘブリディーズ諸島かソロモン諸島出身だったら、その指示はこうなる。「ヘイ、ユーフェラ、ボーイ、ゴウ、ルックン、アイ、ビロンギューアロングデッキ、ブリングン、ミーフェラ、ワン、ビッグフェラ、マースター、ビロング、ブラックマン(おい、そこの君、甲板まで探しに行って、この私のところに黒人の大将を連れてきてくれ)」
初期の開拓者たちの後にメラネシアを航海した最初の白人たち、ナマコ漁の漁師や白檀の売買商人、真珠取り、労働者を集めてまわる者たちがピジン語を発明したのだ。たとえば、ソロモン諸島では、二十もの言語や方言が話されている。交易商人たちがそうした方言を覚えようとしても無理である。というのも、行く先々で言葉が違うし、それが二十もあるのだ。共通の言語が必要だ――子供でもおぼえられる、単純で、実際に使う現地の連中のオツムの程度に合わせて語彙も制限された言語が。交易商人たちは理詰めでそういうものを案出したのではない。ピジン語は条件と状況の産物である。機能が組織に先行している。ピジン語が誕生する前から、まず統一されたメラネシアの言語の必要性があったのだ。ピジン語はまったく偶然の産物だった。しかも、言語は必要性から生まれるという事実に裏づけされたピジン語の由来は、エスペラント*2の信奉者にとっても大いに参考になるだろう。
語彙が限定されるため、一つ一つの言葉には多くの意味が割り当てられることになる。ピジン語でフェラ(やつ)は、一人を指す場合もあるし、可能なあらゆる結びつきで使用されることもある。よく使われるもう一つの言葉は「ビロング(属する)」である。単独では使わない。すべて関係性において使用される。ほしいものは、別のものとの関係で示される。未発達の語彙では表現も素朴になる。雨が降り続くことは、レイン、ヒー、ストップ(雨、やめ)と表現される。サン、ヒー、カムアップ(日が昇る)は誤解の余地がないが、語句の構造自体は変えず、一万通りもの異なる意味を伝えられる。たとえば現地の人が君に、海に魚がいるのを知らせようとする場合、「フィッシュ、ヒー、ストップ(魚、いる)」と言うのだ。イザベル島での取引の最中に、ぼくはこの用法の利便性を悟った。ぼくはペアの大きな(三フィートもある)クラムシェルを二つ三つほしかったのだが、内部の肉は別にいらなかった。もっと小さいクラムの肉でクラムチャウダーを作りたかった。それで、ぼくの原住民への頼は最終的にはこうなった。「ユーフェラ、クラム――カイカイ、ヒー、ノーストップ、ヒーウォークアバウト。ユーフェラ、ブリング、ミーフェラ、スモールフェラ、クラム――カイカイ、ヒー、ストップ(君、クラム――食べ物、いらない、肉はよそに行く。君、持ってくる、ぼくに、小さいクラム――食べるやつ、いる)」
カイカイとは、食い物、肉、食事を指すポリネシア語だ。だが、この言葉は白檀の交易商人によってメラネシアに持ちこまれたのか、ポリネシア人が西に流されて伝わったのかは、よくわからない。ウォークアバウト(歩きまわる)という表現は、ちょっと変わった使い方をされる。ソロモン諸島の船乗りにブームを扱うよう命じると、彼は「ザッツフェラ、ブーム、ヒー、ウォークアバウト、ツーマッチ(あいつ、ブーム、うごきまわる、ひどく)」と言うのだ。そしてその船乗りが海岸での自由を求めた場合、ウォークアバウトするのは自分だと述べるのだ。その船乗りが船酔いすると、彼は自分の状態について「ベリー、ビロング、ミー、ウォークアバウト、ツーマッチ(胃、オレの、むかむか、とても)」と説明するだろう。
訳注
*1: ピジン語(Bêche de Mer English)。Bêche de Merはフランス語でナマコを指す。ソロモン諸島付近はナマコの産地でもあるので、そう呼ばれる。
英語は世界のいたるところで話されているが、現地の言葉と組み合わされ、独特の方言として定着したものも多い。東南アジアから南太平洋にかけてのそれは特にピジン英語と呼ばれる。これは一説には中国語の business がなまってピジンと聞こえるためともされる。
たとえば、日本のテレビドラマで日本語のできる中国人という設定の登場人物が、語尾に「~あるね」という独特の表現を使ったりするが、こういう日本語はいわば「ピジン日本語」になる。その英語版がピジン英語だ。
*2: エスペラント。ポーランドの眼科医で言語学者のL.L.ザメンホフが世界共通の言語をめざして作った人工の言葉。文法は単純明快で、スナーク号の航海の二十年ほど前に発表されたばかりだった。二十一世紀の現代から見ると、なぜ当初予想されたように普及しなかったのかのヒントがここにあるかもしれない。つまり頭脳明晰な人が考え出した論理的で合理的な言語が必ずしも人間にとって現実に必要な言葉になるとは限らない、ということだ。