ジョン・マクレガー著
現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第52回)
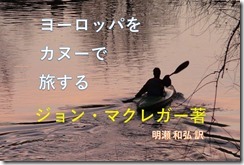
この家のおばあさんという人が出てきた。おっとりとしているが上品で威厳があり、物静かだった。その人が、この闖入者(ちんにゅうしゃ)の受け入れを認めてくれた。年季の入ったオーク材の家具は女性に磨き上げられ光っている。趣味がいい。男連中が熱心に集めたものらしい。太陽がかがやき、水車はまわり、川は流れ続けている。誰もがぼくには親切にしてくれた。「あなたがイギリス人だから」ということだった。
ローマ市民を意味する「キーウィス・ローマーナス」*1というラテン語は、恐怖を与えるときより親切にしてもらうときの方が、ずっとよく威力を発揮する。「互いにかつてのローマ帝国の市民同士」という同胞意識から歓待され、正式に招待してもらったのだが、一向に食事が出る気配はなかった。娘たちがぼくを引き留めるために荷物を冗談半分で隠したりもしたが、ぼくとしては食事ができないのであれば出発せざるをえない。
というわけで、水車小屋に集まっていた全員がカヌーを置いていた場所に移動した。カヌーがあまりにも小さくて、それなのに一人前に小さな旗がひるがえってもるので、若い娘たちは手をたたいて歓声や驚きの声を上げ、漕ぎだすと、さようならと手を振ってくれた。
いろいろ複雑な気持ちが入り混じった状態で、この幸せな楽しい場所を後にした。人里離れたところにある水車小屋での日々の生活がどんなものであるか思いをめぐらせようと努めた。パドルを漕ぎながら、少し感傷的になっていたとしたら、それは、冷たくあしらわれるだろうと予想していた旅行者が思いがけず歓待されたことによるので、そのあたりは大目に見てほしい。
そうした感慨にふけってはいたものの、猛烈に腹も減ってきた。夏の一日に四十マイルもカヌーを漕いできたわけだから、パンとワインとベートーベンだけでは腹の足しにはならないのだ。だから、数時間後に川岸に一軒の宿を見つけると、さっそくオムレツと肉を注文し、なんとか空腹を解消したことは正直に述べておく。岸辺の梨の木が枝を広げていて、その木陰にテーブルが用意された。カヌーは足元の穏やかな流れに浮かんでいる。太陽はさんさんと降りそそぎいでいる。のんびりと身体を休め、ブドウをつまんだり、頭上の枝からもぎとった梨を食べたりしてリフレッシュした。あの水車小屋の姉妹がいつかここにやって来て、今ぼくがしていること、つまり、ぼくが本当はあの家に何を求めていたのかについて真実を知ったとしたら、つまり、腹が減って食事にありつけないかと上陸したのだということを知ったとしたら申し訳ないなという、少し後ろめたい気持ちもあった。
そうして、また「カヌーに乗った」。川に陰を落とす木々や見上げるような岩場や急流、果樹園やブドウ園、いい匂いがただよっている干し草の間を曲がりくねって漕ぎ下り、絶えず変化する光景によろこびを感じながら進むという、これまでとまったく同じ、川下りではおなじみの航海が続いた。そのうち、前方に丘陵が見えてきた。稜線の形状から推測すると、まもなくロイド川に別の川が合流してくると思われた。このあたりのロイド川は、ロンドン南西部のパトニー付近のテムズ川のように、川幅が広く堂々と流れている。一方からリンマート川が流れこんできた。さらに反対側から、アーレ川が合流してくる。ここで三つの川が合流していた。アーレ川が一番大きいようには見えないのだが、川はここからはアーレ川として流れていく。
単なる川ではなく、「由緒正しく、源流から流れてきているアーレ川」というわけだ。スイスを旅行する人は、標高差四十六メートルを流れ落ちるハンデク滝を見のがすことはないので、あれを見た後では、ああ、あのアーレ川か、となるわけだ。この川は二つの氷河から流れ出ていた。その一つがフィンスター・アール氷河で、グリムゼルからそう遠くない。これにはぼくは特別な思い出がある。というのも、登山の拠点として有名な例のグリムゼル・ホスピスの近くの原野で四苦八苦したことがあるからだ。
数年前のある日の午後だった。ぼくは渓谷をローヌ氷河までフルカから二人のドイツ人と歩いてやってきたのだったが、連中がひどいへまをして、そこで中断せざるを得なくなってしまった。で、無分別きわまりないことに、ぼくは彼らと離れて一人で岩山を登った。一人でグリムゼルまで行こうと思ったのだ。これは昼間であればそうむずかしいことではないのだが、ぼくが出発したのは午後六時ごろで、しかも十月だった。三十分ほどで雪が降り始めた。闇夜だし、周囲を白い雪片が舞うという状況だ。とはいえ、なんとも幸運だったことに、道なき道を歩いて山をなんとか登りきったところに、小さな流れがあった。暗闇のなかで何度か渡渉せざるをえなかったが、その小さな渓流が目的の谷に通じていたのだ。やっとグリムゼル・ホスピスの、天国のような灯りが歓迎するように輝いているのが見えてきたので、ぼくはそっちへ向かった。そこにはイギリスから来ている陽気な客たちもいて、ぼくもすぐに輪に加わったのだが、ぐっしょり濡れたズボンを取り替えるため、ウェイターに三シリング六ペンス渡して替えのズボンを買ったのだった。


コメント
[…] 戻る ] [ 次へ ] カテゴリー: ヨーロッパをカヌーで旅する, […]