ジョン・マクレガー著
現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第64回)
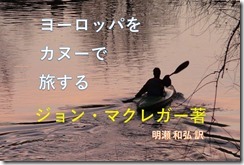
しばらくすると、運河はイル川に流れこんだ。この川はフランスのボージュを通ってライン川に続いている。長さはあるが、流れはひどく遅い。というか、いたるところによどみがあって、単なる水たまりが延々と連なっているみたいで、水面も煮汁のあくのような膜でおおわれていた。となると、この川に長居はしたくない。で、また運河に入り直した。そこで、一人の若者と知り合いになった。本を片手に散歩していたのだ。彼は偶然にもアメリカのカヌーの冒険の本を読んでいたようで、ぼくたちは話をしながら川と岸辺を並んで進んだ。ロックでは、手を貸してくれた。ぼくは、こうやって実際にカヌーで旅をしているのと、本で読む冒険に満ちた物語とはえらい違いだろうと言ったりした! 彼は自分の世界を広げようとしていた。外国を旅したい、特にイギリスを見てみたいと語っていた。それで連れだってレストランまで行き、彼にワインをおごった。料金は二ペンス半だった。若者と別れたときにはもう暗かったので、ぼくはカヌーを水門管理人の家に預けた。そこの息子がイルフュートの村まで連れて行ってくれた。近くに鉄道の駅もあるのだが、背後の丘にはブドウ園が広がり、なんとも牧歌的なところだった。暗闇のなかでも、最高の宿とされた家を見まちがうことはなかった。白い馬という名の宿で、泊まれますかときくと、「個室は無理だけど、三人の相部屋でよければ」という返事だった。
宿の女主人は、ぼくの着古した服と貧弱な荷物を見て、そう答えたのだ。ところが、ぼくがどうやってそこまでやってきたのかを説明すると、評価が一変し、すてきな個室を確保してくれた。まあ、にっこり微笑み、旅をしながら描きためたスケッチを見せてじっくり説明すれば、たいていはこうなるんだけどね。その部屋には大きなベッドが二つあり、小さな水差しと、紙質は悪いがきれいな紙が置いてあった。やっと宿にたどり着いたところで、ぼくは他の客たちに取り囲まれてオムレツを食べた。客というのは荷馬車の御者だったり赤帽だったりしたが、皆が礼儀正しく、ぼくを丁重に遇してくれた。話のセンスもよくて、イギリスの街道沿いにある「パブ」の喧噪(けんそう)とはえらい違いだ
立派な身なりの二人連れがワインを飲みに立ち寄った。憲兵隊だそうだ。二人ともクリミアにいったことがあるということで、やがて興味深い会話が繰り広げられた。やりとりはフランス語だったが、ここの人々は訛(なま)りがきつく、ぼくのようなよそ者にはまるで理解できない。こっちにはわけのわからない言葉で、ぼくについて、あてずっぽうをまじえて語りあっているようだった。で、結局、ぼくは変人ではあるが、一応「ジェントルマン」であり、身分も「悪くない」ということで連中は納得したらしかった。日曜だし、翌日も丸一日、イルフュートに滞在するつもりだと言うと、彼らは本当に驚いていた。今度の航海でもパスポートはずっと持ち歩いていたし、これまで提示を求められたことは一度もなかったのだが、この憲兵隊はパスポートの確認を忘れなかった。今朝は高級ホテルにいたのに、夜にはイルフュートという田舎町の街道沿いの宿屋での宿泊と、すごく変化が激しいが、同じような体験が続くよりは変化のあった方が楽しいというものだ。健康と天候にさえ恵まれていれば、人はどんなこともがまんできる。
夜はまったく静かだった。穏やかで涼しく、のんびりとしていた。とはいえ、それも早朝の四時ごろに雄鶏がときを告げるまでだった。そのニワトリは一番に目が覚めたことを誇らしく告げた。一度、二度、コケコッコーという鳴き声が響きわたった。すると他の雄鶏もそれに呼応して鳴き始め、やがて一ダースもの音調の違う声のニワトリの大合唱となった。それから半時間もすると、人の声が聞こえてきた。女性たちがしきりにしゃべりあっている。で、ドアの留め金がはずされ、カチッという音がし、犬が朝だぞと吠え、厩舎では、やわらかい皮膚をアブに刺された馬が足を踏み鳴らす。しまいにブタがブーブー鳴いた。腹が減ったというわけだ。こうして一日がはじまった。で、そうした生活の流れで集落は眠りからさめ、時間はふたたび穏やかに流れだし、やがて村全体に活気が出てくる。フランスのストーク・ポージス*1とでもいうべき田舎町が、世界の首都でもあるかのように、男の顔も女の顔もまじめくさった表情になっている。
*1: ストーク・ポージスはイングランド南東部のバッキンガムシャーにある田舎町。
詩人トマス・グレイが傑作「エレジー(田舎の墓地で詠んだ哀歌)」を書いた場所としても知られている。
宿泊客があたふたと朝の準備をしている間、ぼくの前にはコーヒーが出された。周囲には四匹の犬と八匹の猫と七羽のカナリアがいて(ちゃんと数えた)、何かを見つめたり、動いたり、さえずったり、ニャーと鳴いたりしているが、それぞれが自分たちのところによそ者が来ているということをしっかり感じているのだった。こうした小さなペットたちが闖入者(ちんにゅうしゃ)をいぶかしげに見つめるので、闖入者(ちんにゅうしゃ)としては「そうか、自分はいま外国にいるんだ」と強く感じざるをえない。


コメント