ジョン・マクレガー著
現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第61回)
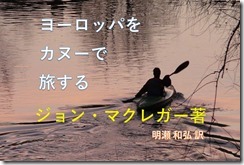
スイスのバーゼルまでは近いので、朝は遅くまで寝て休養をとった。起きると、カヌーを橋の向こうまで運んだ。景色のよい中洲はテラス付きの庭園に作り替えられている。ここでカヌーを水面に浮かべた。この数日というもの、激流を漕ぎくだってきたので、あちこち無数にぶつけたりしている。そういうときの音はとても大きかったので結構な力がかかったと思われるのだが、愛艇はまだ堅牢なままで、とくに大きな問題はなさそうだった。自設計なのでそういう専門家の目で見ても、報告すべき損傷はどこにもなかった。この後の航海でカヌーの船体や板材を酷使し、さらにひどい目に会うことになるのだが、それはまだ先の話だ。
この日の出発では、大勢の女性たちが見送りにきてくれた。女たちは日傘を振り、男たちは万歳と叫んだり喝采したりしてくれた! カヌーは滑るように川を下っていく。「別れの会釈」代わりに、カヌーからは黄色のパドルを頭のまわりで振った。空いている手がないので、友人に対する感謝の意を示すために思いついてやってみた。
レインフェルデンについて、旅行ガイドブックのベデカー誌には「この町を過ぎた下流側で、ライン川はまた急流となり、ホーレン・ハーケン(曲がりくねった急流)と呼ばれる渦ができる」と記載されている。こわい情報で名前もおどろおどろしいが、ここに書いてある「渦」はそう気にするほどのものではなかった。
川に沿って鉄道の線路があった。汽車の音が聞こえる。「ここはまったく未知の荒野で予測もつかない土地」というわけではないことを思い出させてくれる。陸より一段低い位置にある川に浮かんでいると、両側にある土手の向こうが実際にどうなっているかを忘れてしまうことがある。道路から見る風景はよく知られているが、低くなった水面から見上げる景色はまた様子が違っている。どんな景色でも、陸から見た場合、視界は水平線までの距離を直径とする半円になっていて、周囲の空はアーチ状だ。だが、カヌーに座って眺めると、そうした風景は巨大な扇形に姿を変えてしまう。前方の澄みきった水面を視点として、そこから広がりながら両側の岩や木々や苔むした堤防などの土手が斜めに高くのびていく。これはテムズ川のようなふだんから見慣れた川でも同じだ。とくにオックスフォードとロンドンとの間の陸の風景はよく知られていて、旅行者も感嘆したりしているが、同じ場所の光景でも、川を漕ぎ下りながら眺めるとまた違って新鮮に見えてくる。テムズ川のように、曲がりくねって流れながらすばらしい景色を展開している川は少ない。
とはいうものの、ぼくのカヌー旅も、今では文明世界に戻ってきつつあった。よそ者には街並みや宿で体験するすべてのことが物珍しいという、心地よくもシンプルな生活は終わりかけていた。これまでとは対照的に、この文明世界では、天然ではなく合成したロウソクを使っていて芯切りバサミが不要だったり、英語が話せると自称するウェイターが横に座ってぼくの腕をつかんで自信満々に「ビーン・グリーン」(「インゲン豆のような緑色」を指しているらしい)と言ったりしている。彼の英語でぼくが気に入ったのは「花野菜」で、ぼくらが「カリフラワー」と呼んでいるものだ。
あなたがドイツを旅していて、内陸にある村でウェイトレスが大声のドイツ語で話しかけてきたとしよう。彼女の早口のドイツ語は、あなたにはちんぷんかんぷんだ。彼女は自分の言うことがまるで理解できない客を新しい動物でも見たように眺めている。が、やがて客もウェイトレスもどっちも笑いだすことになる。そういう世界を旅してきたわけだ。
だが、ぼくはいま、ライン川で一隻のボートがロープで引かれれているのを見た。舟を引くための道が確保されているのではなく、男たちは草むらを歩きながら舟を引っ張ったり浅瀬を渡ったりしているだけで、ごく素朴な形ではあるのだが、ボートについてこうした光景を目撃するということは、いつでもどこでも上陸できる、自由きわまりないすばらしい森林地帯を抜けてしまったということを改めて悟らされたのだった。
何度か西に向かって曲がった後で、バーゼルの街にある二つの塔が見えてきた。沈みかけている夕日がまぶしくて、正確に見分けることはできなかった。それで、そのまま漕ぎ続けた。九月十四日、川辺にあるホテルにカヌーを引き上げた。バーゼルの街にかかっている橋はすぐに物見高い通行人や野次馬であふれた。ここは、例のずぶぬれになった四つの漕ぎ座がある五人組のボートが数週間前に到着したところだ。建物の所有者は、また別のイギリスのボートが来たというので喜んでいた。今度はずっと小さなボートで、乗っているのも一人きりだったが、こっちは先を急ぐ風でもなく服も濡れてもいない。ぼくは街を散歩した。とある教会に入ってみた(スイスのバーゼルだから、むろんプロテスタントの教会だ)*1。ちょうど洗礼式が行われているところで、大勢の人が集まっていた。赤ん坊は母親から父親へ、教会の聖職者(クラークからミニスター)へと手渡しやすいように枠付きの台に寝かされていた。ぼくは赤ん坊という存在には畏敬(いけい)の念さえ抱いているので、こういう風に、どこか機械的に赤ちゃんを取り扱うことには強い違和感を感じてしまう。
*1: ドイツのマルティン・ルターと並ぶ宗教改革の主導者だったツヴィングリやカルバンはスイスの出身で、当時のスイスにはプロテスタントが多かった。
現在のスイスでは、イタリアやスペインなど南欧系の労働者の移住により、宗派統計上はローマ・カトリックがプロテスタントを上回っている。
洗礼式が終了するとすぐに、幸福そうなカップルが前に進み出た。これから結婚するのだ。新郎はぱっとしない風采だったが、新婦は美しかった。とはいえ、もう若くはなく、五十五歳くらいに見えた。花嫁の付き添い人や七面倒くさそうな関係者の姿は他になかった。式がすむと、このカップルは、女たちがクスクス笑うなかを歩いて出て行った。花婿は次にどうしたらよいのか、よくわかっていないらしく、新婦の前後を歩いたり横に並んだりしていたが、どこか居心地悪そうで、結局は彼女のそばからつかず離れずの斜めの位置を確保して歩いていき、二人とも別の建物に姿を消した。これから結婚生活をはじめる儀式として、これほどロマンティックの対局にあるものは見たことがない。とはいえ、こういう式にも取り柄はある。うっとうしい「両家の顔合わせの食事会」で、新しく親戚になる二組の人々が相手を探りあうという、うんざりするような儀式がないのだから。そういう食事会では、腹もへっていないのに一緒に食事をし、相手のしょうもない話に耳を傾けているふりをすることで、互いに親密になることを期待されているのだ。とはいえ、ぼくとしては、旅先で出会った人々の不可解な風習なんかを批判したいわけではないので、宿の話に戻そう。喫茶室で、あるフランス人と出会った。その人はロンドンで生活していたことがあり、これからロンドンに行くという二人のメキシコ人に現地のホテルについて説明しているところだった。ロンドンの「コーヒーハウス」や「レスター・スクエア」にあるホテルについての彼の説明は笑えた。「スクエアはイギリスではスクアと発音されるんだ」などと言っていた。


コメント
[…] 戻る ] [ 次へ ] カテゴリー: ヨーロッパをカヌーで旅する, […]