ジョン・マクレガー著
現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第80回)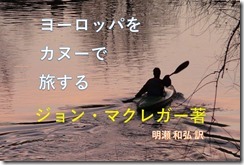
第十四章
運河を通ってナンシーまでやって来た。美しくて古い町だ。カトリックの大司教や陸軍元帥がいて、立派なホテルが一軒に大きな洗濯場が何か所かある。太鼓やラッパに氷菓子など、人生を豊かにする品すべてがそろっている。だが、ナンシーという町が軽騎兵の部隊を招致したことにより、こうしたものすべてが脇に追いやられてしまった! 大聖堂では、イタリアだったか、前にも話したのよりさらに悪趣味なミサが行われていた。ミサを執行する司祭が三十人以上もいて、この物静かな老人たちは豪華で派手な刺繍(ししゅう)をほどこした服をまとい、ラテン語をつぶやきながら、頭を下げたり、向きを変えたり、しかめっ面を浮かべたりしているのだが、実際にあらゆる限度を逸脱していた。こうしたことは、キリストに代わって執り行われるという形の聖餐式(せいさんしき)に参列し、「わたしを記念するため、このように行いなさい」*1という言葉の真実の解釈として、こんな茶番を受け入れざるをえない人々にとって侮辱でしかない。
*1: 新約聖書の「コリント人への第一の手紙」の11章24節。
いわゆる聖餐式(せいさんしき、ミサ)の奥義ともいうべき、パンを裂いて祝福する儀式についてのキリスト自身の言葉とされる(訳文は日本聖書協会発行の新訳聖書より)。
大勢の会衆はほぼ全員が女性で、昔の聖人をたたえる若い神父の雄弁な説教に聞き入っている。古代のお偉い人物が最も尊敬されるべき聖職者であった可能性はあるものの、実際のところ今の修道院で出会う聖職者の多くとそうたいして違ってはいまい。ヨーロッパやアジアやアフリカで聖職者に頻繁に接した経験からすると、そういう聖職者の一人が近寄りがたいほど傑出してすぐれていたと過度に美化されるのを目にすると、つい笑ってしまう。とはいえ、おそらく、この聖職者様は毎日の沐浴をきちんと務めることによって他とは違うんだということを明確に示し、クリーンな人物であるという稀(まれ)な評判を得ていたのだろう。
午後になると、この聖人の遺骸は、何千人もの女と少数の男の行進と共に通りを運ばれて行った。参列したご婦人方のうち、白いモスリン生地の服を着用した人が何百人もいて、ゆっくり行進しながら聖歌を口ずさんでいる。見物人は全員、帽子を脱いでいる。ぼくの方は、痩せこけた修道士の体が邪魔になって、礼拝の様子がよく見えなかったので、麦わら帽子をかぶったまま脱がなかった。
社会性を持って暮らしているフランス人は公共の宗教というべきものを持ち、集団で礼拝し、それとわかる行動や色彩や音を持っているのに違いない。そうした、深い献身と深い沈黙は北の地方には適している。気温が高く活動を控えがちな低緯度地方でも静かな礼拝というものは存在しうるが、やはり太陽がさんさんと輝く地方向きとはいえない。三十年ほど前、ケンブリッジの学生だったぼくらの仲間のうちでも優秀なやつが、イギリスが島国であることとイギリスの気候が国民の気質に与える影響についての論文を読んでくれたことがある。たとえば、ナンシーのような田舎町のフランス人についていえば、快適か否かはほぼすべて天候に左右されるので、雨や雪が降ると気分も落ちこんでしまうだろう。だから、そうしたフランス人がイギリスに行ったとすると、英語がうまくできなくて誤解されて人に笑われたり、夕食には二皿しか料理がでなかったりするし、まずいコーヒーを飲むはめにもなる。夕方に営業している屋外のラウンジなどないし、そういうときはイギリスの家庭生活を見る機会だと言われたとしても招かれることはない(英国の家庭に呼ばれるフランス人はほとんどいない)。そういう外国人の不運な境遇は直接にはイギリスの気候のせいであり、イギリスのあるグレートブリテン島が、イギリス人はみな霧と木綿とたばこの煙に包まれて、すべてがみじめだという印象を与えたとしても何の不思議もない。
ナンシーからマルヌ川まで、カヌーを貨車で運んだ。貨車の方が遅いので、それが着くまでの間、先着していたぼくはフランスのアルダーショットともいうべき軍事施設があるキャンプ・デ・シャロンを訪ねた。駅からバスが出ている。長く埃っぽい街道筋に人家はほとんどなかった。たまにあると、なんともお粗末で、手で押しただけで、そのまま押しつぶされてしまいそうだった。ここは軍事地区というわけではないのだが、軍事施設関連の商人たちが住み着いている町で、たいていの軍事基地の周囲にはこういうところがある。で、ぼくがやって来たのは「プレース・ソルフェリーノ」というところだった。ここに「マラコフ通り」というのがあり、宿屋の印はフランス人が切り落としたブタの尻尾を持った中国人だった。ここの軍事施設は大平原のど真ん中にあって、埃っぽかった。大地の色も白っぽくて、目が痛いくらいにまぶしい。今度の航海で一番暑い日ではあった。とはいえ木陰もあったし、広々とした大地は一面の草原にもなっていた。ここは陸軍の演習地だ。今は亡き皇帝が丘の上の東屋から軍の行進を見守ったりしていたところだ──もっとも、その軍もやがては恐怖にかられて逃げ出してしまうことになってしまったのだが。
